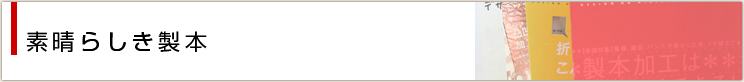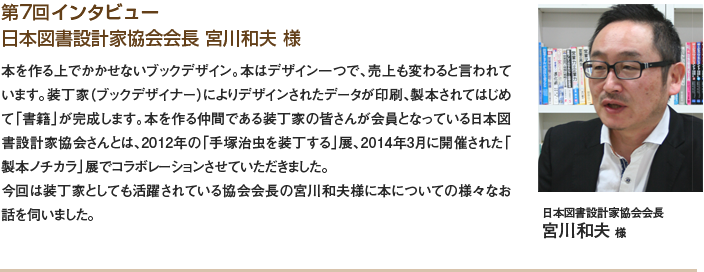いろいろな製本会社の方々とお付き合いさせていただいて感じたのは、製本会社の皆さんの職人気質ですね。最初は「うーん」と渋い顔をされるんですが、「これは難しいですか?できないですかね?」というと「やる!」といって、チャレンジしてくださる。どうやったらよくなるかって、すごく考えてくださるんですね。私たちのアイディアをなんとか形にしよう、応えようとしてくれる、本当に職人だなと思って感動しました。製本の量産のためにどんなにシステマティックな工程になっても、そういうところは継承してDNAを残していっていただきたいですね。技術がなくなるということは、そこで歴史が途絶えるということです。日本人は貴重な技術を、わりと容易く無くしてきたという歴史があるので。
私たちの発想を製本会社のみなさんの技術力で具体化し、それで儲かると本当は一番いいんですけれど・・・なかなか現状は厳しいですが、これから大量から小量の時代に変わると何か可能性が出てくるかもしれませんね。
個人的にイラストレーターと組んでつくった本を持ってきました。『RED』というまっ赤な本です。1冊ずつ、R:ロマンティック、E:エロティック、D:ドラマティックという3部作になっていて、全ページに手描きのイラストレーションを2000枚以上描いてもらっています。僕が卒業した武蔵美の基礎デザイン学科のOBが、毎年1回「カラーパーティー」という展示をするんですが。このときテーマが「RED」だったんです。だから、当時仕事でお付き合いのあった印刷会社の方に、「ちょっとこういう物を作りたいんですけど」と頼んで、竹尾さんにも紙を協力してもらって。ただただ分厚いまっ赤な本を作ったというわけです。
展示が終わった後で、「何かもっとできないかな」と思い、知り合いのイラストレーターに「ちょっとこの中に、絵を描いてみませんか?」と頼んで、それで2年半ぐらいかけて1ページずつスミで描いてもらったんです。イラストレーターやデザイナーは、これがまず手描きだということにびっくりします。これひとつも下書きがないんですよね。テクニックもさることながら、世界観が素晴らしい。このイラストレーターも、今では売れっ子になっています。
これを展示していた時、欲しいという人が現れたんです。いくら払えますかと聞いたら20万円くらいならと、でもそれじゃあ売れないし、元々売る気ないし(笑)。
最初は単なる赤い本だったものが、20万円でも欲しいと思う価値が生まれてきたわけです。
近い将来、紙の本って段々かけがえのないものになって行くんでしょうね。今みたいにたくさんは出回らず、欲しい人にだけひっそり、なんてね(笑)。それで我々は食べていけるのか。そこが問題です・・・。
--最後に、電子メディアのお話を少し。電子メディアについて、どうそれに対応していくかというのは、何かありますでしょうか?

ひとつは、協会として取り組んでいるというか、考えとして言いますと、紙の本をまず作って、それを電子化する際に、ジャケットのデザインをそのまま無断で使うということはやめてほしい。そういう要望書はあげています。あとは当協会を始め、東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)や日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)などと一緒に、美術著作権連盟(美著連)という団体に加盟し、様々な権利問題に取り組んでいます。具体的な例としては、我々の働きかけにより、国立国会図書館で「原装コレクションの構築(装丁を全部残した書籍の収集・保存)プロジェクトが立ち上がりました。これは従来本の保存において、ブックジャケットが外されていたものを、それも含めて「書物」であるというという主張を行い、認められたという画期的な取り組みです。
今後電子化される本ということで考えると、資格を取るための本などの、いわゆる情報の価値で売る本などは、電子書籍化がどんどん進んでいくのでしょうね。あとは辞書とか。僕はいまだに紙の辞書を引いてしまうんですが、うちの子どもたちは、紙の辞書自体を持っていません。学校でも、高校に入学した途端に、電子辞書を買わせますから。
生まれた時から携帯やスマホに慣れている人たちが、大人になった時にどうなるのかというのもありますね。うちの長女は、今大学4年なんですが、まあ本を読まないです。もうスマホばっかり。インターネット社会というのは、欲しい情報をすぐ入手できるという利便性の反面、その中だけで完結し、分かったつもりになってしまう危険性があるように思います。それだけではないもっと深いものを、自ら探して見つけ出す能力が欠けてしまうような気がします。
紙の本のある場所、つまり書店とか図書館という「知の森」をもっともっと彷徨う楽しさを知って欲しいなあ。
今後、電子書籍がどんどん広がっていくと、さらに世の中はドラスティックに変わるんじゃないですか。われわれもそうですが、紙の本で飯を食っている人たちは、やはり怖い。死活問題ですからね。
でも、今回の製本ノチカラ展で、まだまだ紙の本には可能性があるということが認識できましたので、皆さんと一緒に、より創造的なチャレンジをしていきたいと思います。